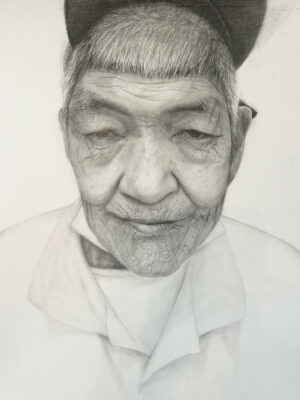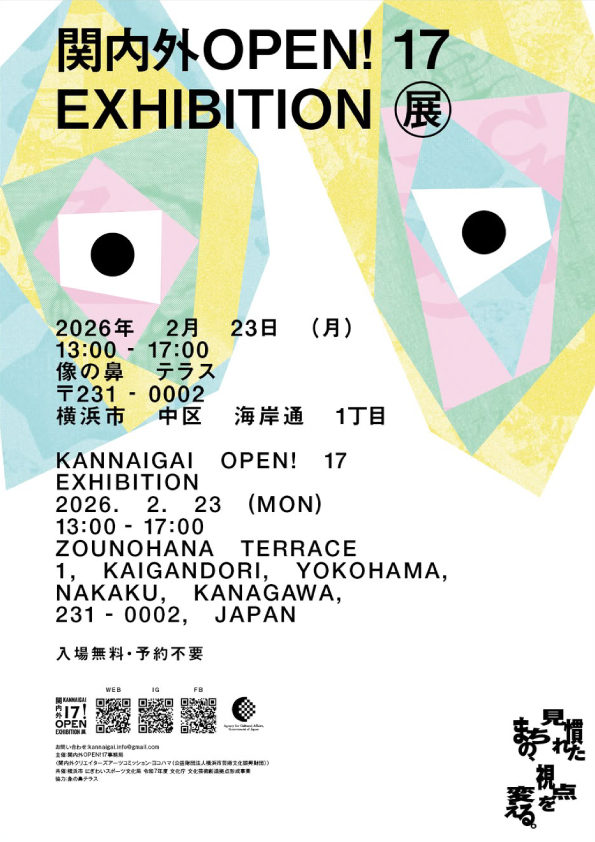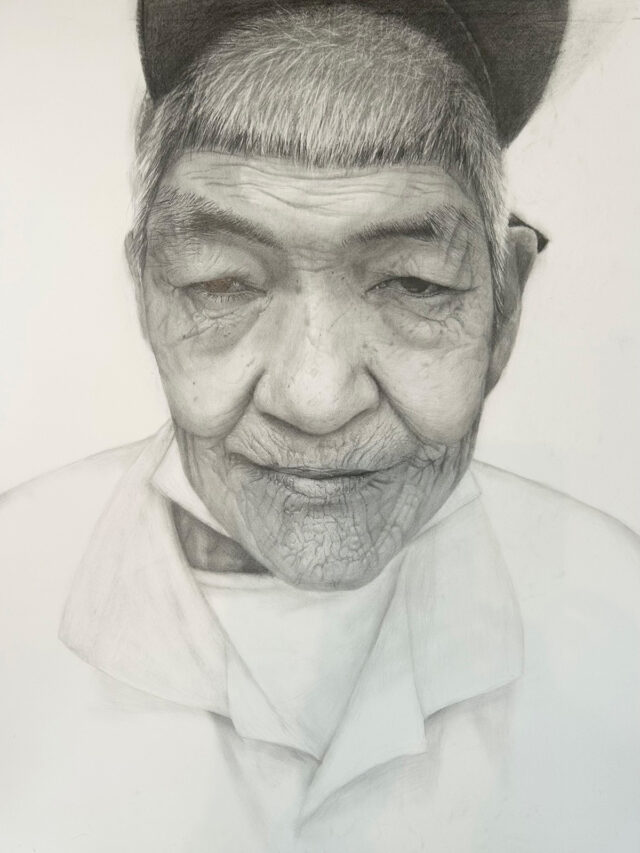相談窓口
横浜で活動するアーティストやクリエイター、企業や行政等からのご相談に対応しています
アーティスト・フェロー
これまでキャリア形成を支援してきたアーティストを紹介します
トピックス
アーツコミッション・
ヨコハマとは
アーツコミッション・ヨコハマ(ACY)は、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が運営する「芸術文化と社会を横断的に繋いでいくための中間支援」のプログラムです。

事業紹介
相談
横浜で活動するアーティストやクリエイター、企業や行政等からのご相談に対応しています
アーティスト・クリエイターの方
- 創作の場、発表の場を探している
- 活動するための情報が知りたい 他
企業・行政・教育機関の方
- クリエイターを探したい
- 建物またはスペースを再活用したい 他