*この記事は、ACYが2021年7月13日にnoteに投稿した記事を移行したものです。
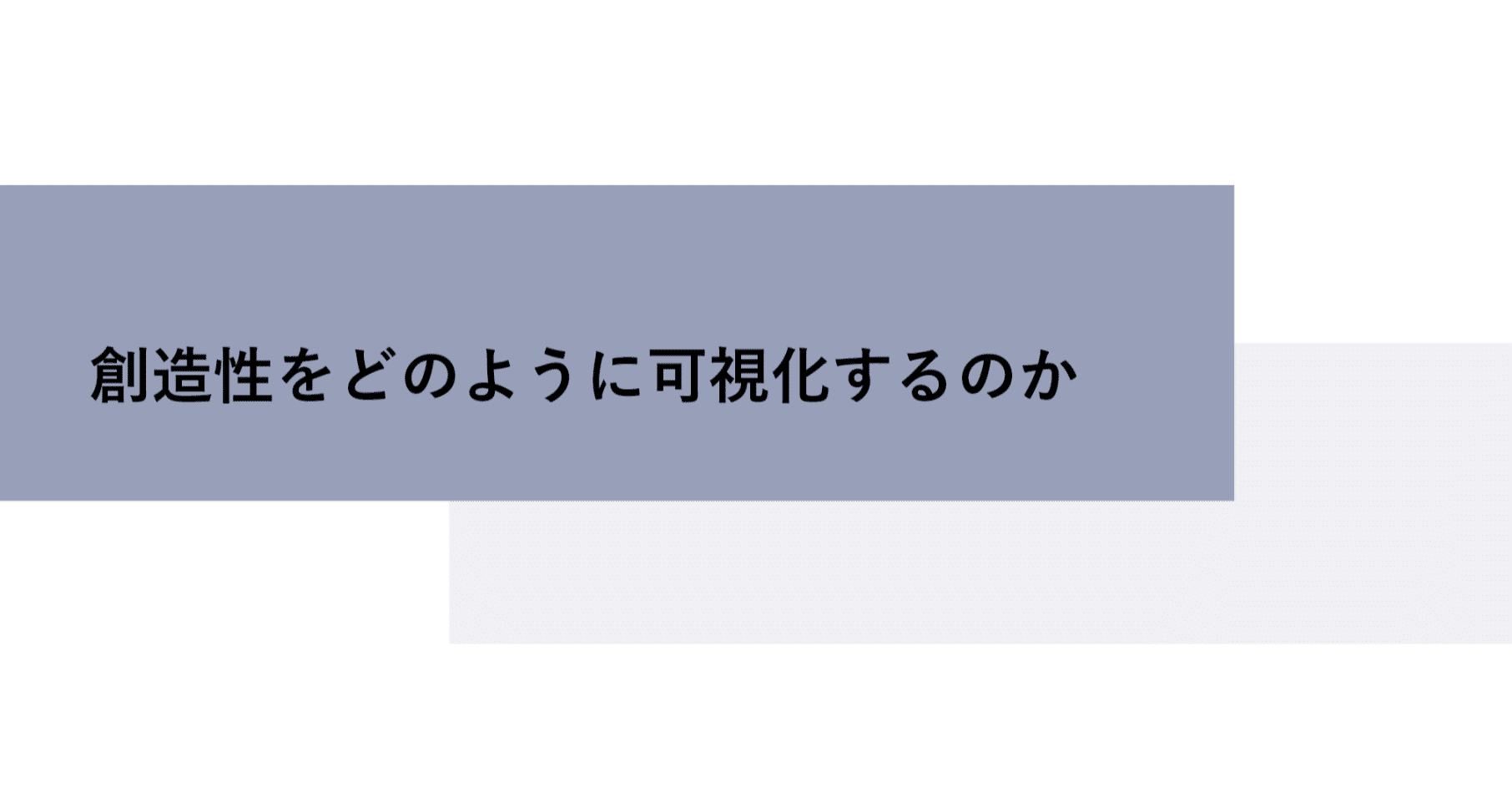
横浜は、異国情緒あふれる港町、みなとみらいのビル群の風景としてよく知られていますが、郊外にいくと古墳や宿場町といった旧跡があり、鉄道沿線に住宅が立ち並び、森や川、広々とした公園など自然が豊かで四季折々の風景があります。
YokohamArtLifeは、こうした横浜ならではの環境を生かして、アートプロジェクトを実施し、地域と共に芸術体験を深めていくことを試みました。その結果、予期せぬコロナウイルス禍のなかでも、各地で芸術と住民の出会いを生みだし、寄り合える居場所やそこで行われる芸術活動の大切さを地域と共有することができました。
このマガジンでは、すでに発行したYokohamArtLifeの「2019年度-2020年度 横浜市芸術創造特別支援事業リーディング・プログラム YokohamArtLife ヨコハマートライフ報告書」(PDF:28MB)から、実際の活動や仕組みづくりに協力してくださった学識者の言葉を抜粋して、ご紹介します。
アートが人に与える価値を指標化するという試みについて、心理学的アプローチの見地から、専門家の岡田猛先生(東京大学大学院)に寄稿していただきました。
アートに関わる活動やプログラムを「評価する」というと、怪訝な顔をされたり、抵抗感を示されたりすることがしばしばあります。またその際によく耳にする反論として、「アートの効果は簡単に数値化できるものではない」「アートの受け取り方は、人によって多様だ」といったものが挙げられます。
これらはいずれも「評価」を誤解しているか、狭く捉えすぎていると言えます。詳しくは後から説明しますが、評価とは数値化することではありませんし、作品からの受け取り方の多様性を否定するものでもありません。本稿では、評価がなぜ大事であるのかを述べた上で、アートに関わる実践を心理学的なアプローチから評価する方法について、簡単に紹介します。
「評価」という言葉は、一般的には、「価値を定める」「採点する」といったニュアンスで用いられることが多いかもしれません。特に税金が投入されていたり、地域コミュニティを巻き込んで展開したりするものであれば、その成果を可視化し、説明責任を果たすことも重要です。しかし、評価の役割はそれだけではありません。
評価の大きな意味として、当該の活動やプログラムをより良いものへと改善していくための示唆を得るということがあります。学習科学の領域で、「design-based research:DBR」という手法が提案されています(Barab、 2014*1)。この手法では、まずこれまでの実践の経験や何らかの理論的な知見に基づいて教育実践をデザインします。そして、実践を展開していくことと並行して、実践のプロセスや成果を評価し、実践の中での学習者の学びの内容や、実践がうまく機能していない部分などを同定します。その評価に基づいて、実践の内容や方法を修正し、実践のデザインの仕方についても省察します。その後も実践を企画・実施して評価するというサイクルを何度も繰り返し、実践をデザインするための指針や原則などを構築し、実践内容とその理論的フレームワークの両方の精度を高めていくのです。
この時、評価はそれ自体が目的ではなく、あくまで実践をより良いものにしていくための「手段」となります。したがって、ただテストを実施して「得点化」「数値化」すればよいわけではなく、プログラム改善のための示唆が得られやすいような方法で検証を行うことが重要になります。アートの活動にも、このDBRの考え方は有益だと考えられます。すなわち、ワークショップやプロジェクトを展開していく過程で、適宜評価の楔を打ち込むことで、活動そのものを修正でき、また以後の活動をデザインする上での指針となるフレームワークをより強固なものにすることができます。
それでは、そのようなアートに関わる実践の評価は、どのように行ったらよいでしょうか?どのように評価のための指標を設けたらよいでしょうか?評価のあり方をデザインする第一歩は、実践の目的、すなわち、参加者・鑑賞者に何を体験させたいのか、何を持ち帰って欲しいのかということを明確化することです。まずはその軸から、実践のプロセスや効果を捉える指標について検討することになります。
ところが、この最初の部分が、アートの活動における評価を難しくする大きな要因になりえます。例えばアートのワークショップでは、他の多くの教育実践や学習支援の活動とは異なり、何か特定の理解させたいこと、身につけさせたいことが明確に存在しているわけではありません。むしろ、アーティストやファシリテーターによる「提案」に対して、参加者はそれぞれ異なるかたちで「触発」され、多様な方向に考えを巡らせたり、刺激を受けたりということが頻繁に起こり、それが歓迎されます(岡田、 2016*2)。したがって、アートにおいては、目標を一つに定められず、それゆえ「目標への到達度」という枠組みの評価は馴染まないということが起こるのです。
しかしながら、「受け手の多様性」を尊重した形で評価を行うことも可能です。例えば、活動後のアンケートやインタビューにおいて、ワークショップの体験を通して何を考えたか、どのような刺激を受けたかを尋ね、参加者たちの中に生起した触発のバリエーションを取り出すことはできます。あるいは、参加者の振る舞いの変化や、実践中に生成された会話に着目することで、参加者の体験のプロセスやパターンを追跡することもできます。そこから、ワークショップの中で参加者に体験させたいことをデザインしたものの、その内容が不十分だったり、参加者にうまく伝わっていなかったりする部分を特定したり、逆に意図していなかった面白い反応を拾い上げることができるかもしれません。もちろん、評価を行うに際しては、実践を展開させていくこととは別のコストも要しますが、実践者自身が省察をするだけでは気づきえなかった、広がりのあるフィードバックを得ることができます。
最後に、評価を行うことの別の重要性を一つ指摘して本稿を閉じたいと思います。残念ながら我が国では、芸術文化の意義が十分に認められていない現状があります。文化芸術に費やされる予算の割合は先進国の中でも最低レベルで、学校の芸術系科目の時間数もますます削減されています。それゆえ、芸術文化の意義を広く知ってもらうために、アートに関わっている人がアートの重要性を実感し、アートの実践の多様な効果のエビデンスを示しながら発信する努力を重ねていくことが、まさに今求められていると言えます。今回のYokohamArtLifeの取り組みも、そこにつながる取り組みになればと思います。
*1 Barab, S. Design-based research: A methodological toolkit for engineering change. Handbook of the learning sciences, 2, 2014, pp. 233-270.
*2 岡田猛『触発するコミュニケーションとミュージアム』中小路久美代・新藤浩伸・山本恭裕・岡田猛(編)、「触発するミュージアム:文化的公共空間の新たな可能性を求めて」、あいり出版、2016年、2-10ページ。
岡田猛(おかだ・たけし)東京大学大学院 教育研究科・情報学環 教授

岡田猛研究室のレクチャー(第1回YALルーム)講義録は こちら。
YALが目指すゴールに向けてどのような歩みがあったのか、そして、各参加団体が自分たち自身の活動をどのように振り返っているのかは、以下の報告書に取りまとめていますので、ご覧いただければさいわいです。
▶すべての取り組みの報告書は、こちらから(ACYウェブサイト)

